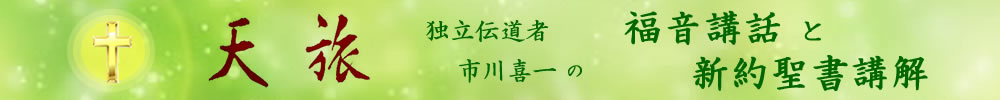
第二節 別の同伴者の到来
15 「あなたたちは、わたしを愛しているならば、わたしの命令を守るであろう。 16 わたしは父にお願いしよう。父は別の同伴者をあなたたちに与え、その方がいつまでもあなたたちと一緒にいるようにしてくださる。 17 その方とは真理の霊である。世はその霊を受けることができない。世はその霊を見ることもないし知ることもないからである。あなたたちはその霊を知っている。その霊はあなたたちのもとに留まり、あなたたちの中におられることになるからである。
18 わたしはあなたたちを孤児とはしない。わたしはあなたたちのところに戻って来る。 19 もうしばらくすると、世はもうわたしを見ないが、あなたたちはわたしを見る。わたしが生きているので、あなたたちも生きるようになるからである。 20 その日には、わたしがわたしの父の内におり、あなたたちがわたしの内に、そしてわたしがあなたたちの内にいることが分かるであろう。 21 わたしの命令を保持してそれを守る者は、わたしを愛する者である。わたしを愛する者はわたしの父に愛されることになり、わたしもその人にわたし自身を現そう」。
22 イスカリオテでないユダがイエスに言う、「主よ、わたしたちには御自分を現そうとされるのに、世には現そうとされないのは、どうしてですか」。 23 イエスは答えて彼に言われた、「誰でもわたしを愛するならば、わたしの言葉を守る。そうすると、わたしの父もその人を愛されて、わたしたちはその人のところに行き、その人のところに住む。 24 わたしを愛さない者は、わたしの言葉を守らない。実に、あなたたちが聞いている言葉はわたしの言葉ではなく、わたしを遣わされた父の言葉なのである。
25 これらのことは、わたしがあなたたちのもとに留まっていたときに語ってきた。 26 だが、かの同伴者、すなわち父がわたしの名によって遣わされる聖霊であるが、その方があなたたちにすべてのことを教え、わたしがあなたたちに話したことを思い起こさせてくださる。
27 わたしはあなたたちに平安を残していく。わたしの平安をあなたたちに与える。世が与えるようにではなく、わたしが与える。あなたたちは心を騒がせず、恐れないでいなさい。 28 あなたたちは、『わたしは去っていくが、また戻って来る』とわたしが言うのを聞いた。もしわたしを愛しているのであれば、あなたたちはわたしが父のもとに行くことを喜んだことであろう。父はわたしよりも大いなる方であるから。 29 そして今、ことが起こる前にあなたたちに言っておく。ことが起こったとき、あなたたちが信じるようになるためである。 30 あなたたちの間で多くを語ることは、もはやないであろう。世の支配者が来るからである。彼はわたしに何のかかわりもない。 31 しかし、わたしが父を愛していることを世が知るようになるために、わたしは父がお命じになったとおりに行うのである。さあ、立て。ここから出ていこう」。
別の同伴者
「あなたたちは、わたしを愛しているならば、わたしの命令を守るであろう」。(一五節)
イエスは「わたしを愛しているならば」と言われます。「わたしを愛する(または愛さない)」という表現は、この段落で6回繰り返されています(一五、二一、二三、二四、二八節)。イエスを愛するとは、イエスを復活者キリストと信じて告白し、全身全霊をもってこのイエスに自分を委ね、このイエスと結ばれて生きること(すなわち信仰)をヨハネ流に言い表したものです。イエスを愛するならば、その愛の表現として必然的に愛する方の言いつけを守ることになるはずです。「わたしを愛する者は、わたしの命令を守れ」という命令文ではなく、「守るようになる」という事実を指す未来形です。復活者イエスと結ばれて生きる者は、必然的にその方を生かしている質の命に生きないではおれません。これは命の必然です。
イエスを愛する者が守るようになる「わたしの命令」とは、先にイエスが弟子たちお与えになった「新しい命令」を指しています。すなわち、「わたしがあなたたちを愛したように、あなたたちも互いに愛しなさい」という命令です(一三・三四)。そこでも述べたように、「命令」というよりは「言いつけ」というような意味でしょう。イエスが愛された質の愛をもって互いに愛し合うことだけが、イエスの弟子である標識となります。
< !-- ==================== -->
「わたしは父にお願いしよう。父は別の同伴者をあなたたちに与え、その方がいつまでもあなたたちと一緒にいるようにしてくださる」。(一六節)
そうすれば、すなわち弟子たちが言いつけを守って歩んでおれば、「わたしはこうしよう」という形で、去って行かれた後イエスの側でしてくださることが語り出されます。この節は「そうすればわたしの方は」という対照を強調する形で始まっています。父のもとに行かれたイエスは、父に願ってくださり、父が「別の《パラクレートス》」を派遣してくださるにようになるというのです。この《パラクレートス》は、普通「助け主」(文語訳、協会訳、新改訳)とか「弁護者」(塚本訳、新共同訳、岩波版)と訳されるギリシア語です。 英語では Comforter, Helper, Counselor, Advocate などと訳されています。
《パラクレートス》は、《パラ》(傍に)と《クレートス》(呼ばれた者)から成る語で、ギリシア語の世界では法廷で訴えられている者を弁護する「弁護士」の意味で用いられ、ヘレニズム世界の一般的な用法では、「助け手」という意味で用いられることが多い語ですから、そう訳すのは自然なことです。たしかに共観福音書に伝えられているイエスの語録には、聖霊が法廷で証しを立てる信徒のために語ることを教えてくださる「弁護者」とされているところがあります(マルコ一三・九~一一、マタイ一〇・一八~二〇)。
しかし、「別の」という説明は、ここで語っておられるイエスが自分を弟子たちの《パラクレートス》としておられて、自分が去っていった後に、自分に代わって弟子たちと「一緒にいて」、自分がしたように教え導き助ける方を指しておられることになります。そうすると、弁護士とか助け手など特定の働きを指す名称よりも、さらに広い意味に理解するのが適切ではないかと考えられます。ここでは、《パラクレートス》(呼ばれて傍にいる者)という語意を広く理解して、あえて「同伴者」と訳しています。この訳語は、この方が派遣される目的が「いつまでもあなたたちと一緒にいるようにしてくださる」ためとされていることからも、許されるのではないかと考えます。
この「同伴者」は、地上のイエスのようにいつかは去って行かれる同伴者ではなく、「いつまでも」一緒にいてくださる同伴者です。いつまでも一緒にいて、地上のイエスが弟子たちにしてくださったように、教え、導き、励まし、助け、癒してくださる方です。その「別の同伴者」のことが、以下の節で詳しく語られます。
「その方とは真理の霊である。世はその霊を受けることができない。世はその霊を見ることもないし知ることもないからである。あなたたちはその霊を知っている。その霊はあなたたちのもとに留まり、あなたたちの中におられることになるからである」。(一七節)
ここで、イエスが「別の同伴者」としておられる方は聖霊であることが、明確に語り出されます。そして、弟子たちが受けることになる聖霊が、ヨハネ福音書独自の「真理」《アレーテイア》という語を用いて「真理の霊」と呼ばれます。《アレーテイア》とは、この福音書においては、影とか型に対して実質のある本体、英語のrealityに近い意味で用いられており、「真理の霊」とはそれを受ける者を「真理」に導き入れる霊(一六・一三)、霊の次元で実質的な体験を与える霊という意味になります。イエスが去られた後、弟子たちが受けることになる「別の同伴者」がどのような働きで真理に導き入れてくださるのかは後で語られるようになりますが(一六・一二~一五)、ここではその方の「同伴者」としての在り方が描かれます。
この一七節では、ギリシア語で「霊」は中性名詞であるので、「真理の霊」を指す代名詞として、原文では繰り返し「それ」が用いられています。しかし、「真理の霊」は「同伴者《パラクレートス》」として来られるのですから、イエスご自身と同じように人格的存在であり、「彼」で指す必要があります(RSVのように)。ここでは代名詞を用いないで「その霊」という名詞を繰り返して訳しています。
世とイエスの弟子たちの違いは、この霊を受けていない者たちと受けている者たちとの違いです。イエスを拒んでいる「世」は、どのような修行や努力をしても、この霊を体験することはできません。この霊は、「父がイエスの名によって遣わされる」霊であるからです(一四・二六)。それに対して、「あなたたち」すなわち弟子たちは、「その御霊を知っている」と言われます。ここの動詞は現在形です。著者は御霊によって生きているヨハネ共同体の現実を念頭に置いて語っています。以下の文の動詞は現在形と未来形が混在していますが、それは著者がヨハネ共同体の現在の体験を念頭に置きながら、この時点でイエスが復活後の未来を語っておられるという構成をとっているからであると見られます。
「その霊はあなたたちのもとに留まり、あなたたちの中におられることになる」と言われます。「もとに留まる」は現在形で、「中におられることになる」は未来形です。ただし、この場合の現在形と未来形は、地上のイエスと共にいる現在の体験と、「別の同伴者」が来られる時に起こる未来の体験の違いを示すものではなく、両者共に「別の同伴者」が来られる時のことを語っているのですが、その同伴者が「いつまでも一緒にいてくださる」という時間を超えた現実を語る現在形と、地上のイエスが語っておられる時からすれば未来であることを示す未来形になっているだけであると理解すべきでしょう。
ここでこの「別の同伴者」が、あなたたち「のもとに」あるいは「と一緒に」(ギリシア語では《パラ》)留まると言われるだけでなく、あなたたち「の中に」(ギリシア語では《エン》)いてくださるようになると語られています。この《エン》を「あなたたちの間に」と理解すれば、キリスト者の共同体すなわちエクレシアの中に御霊がおられて働いてくださることを指すことになります。もちろんこれも真理です。しかし、この福音書全体の主張からすれば、「あなたたち一人ひとりの中に」宿ってくださると理解すべきでしょう。聖霊は、わたしたち一人ひとりの中に内住して、わたしたちを教え、導き、助け、癒し、信仰と愛と希望に生かして下さるのです。この御霊によって生きることで、キリストに属する者は世から分かたれます。
戻って来られるイエス
「わたしはあなたたちを孤児とはしない。わたしはあなたたちのところに戻って来る」。(一八節)
「同伴者」が誰もない状況が「孤児」という比喩で語られて、イエスが去られた後に「同伴者」が来られることが改めて約束されます。ところが、ここでイエスは、「わたしはあなたたちのところに戻って来る」と、自分が弟子たちのところに戻ってきて「同伴者」となることを約束しておられます。したがって、先に約束された「別の同伴者」はイエスご自身であることになります。ただ、地上におられたときのイエスとは違い、復活されたイエスが聖霊という形で弟子たちと一緒におられることになるのです。「別の同伴者」とは、御霊として働かれる復活者イエスです。「もうしばらくすると、世はもうわたしを見ないが、あなたたちはわたしを見る。わたしが生きているので、あなたたちも生きるようになるからである」(一九節)
「もうしばらくすると」というのは、直後に起ころうとしている死と復活の出来事を指しています。世の人は身体をもった人間しか見ることができないのですから、死んでこの世からいなくなるイエスを見ることができなくなります。また、この世のすべての人が見るようになる、黙示思想的な終わりの日の「人の子」の来臨(黙示録一・七)も、ここでは視野に入っていません。ヨハネ福音書は、聖霊の到来によって、聖霊を受けて復活者キリストを見ている神の民と、聖霊を受けることがないので復活者キリストを見ることがない「世」が峻別されるとします。黙示思想が待ち望んだ終わりの日の裁きが、このような形で到来しているとされるのです。
世はもうイエスを見ることはありませんが、弟子たちは復活されたイエスを見ることができます。ここの「見ない」も「見る」も現在形です。著者は世とキリストの民の現在の対立を見ています。そして、その理由を示す文が直後に続きます。
「わたしが生きているので」の「生きている」は現在形です。これは、イエスが復活して永遠に生きておられる事実を語る現在形です。そのイエスに結ばれる「あなたたちも生きるようになる(未来形)」、すなわち復活されたイエスの命にあずかり、イエスと同質の復活の命に生きるようになり、復活されたイエスを現実として体験的に知るようになります。これが「わたしを見る」と言われる理由です。
「その日には、わたしがわたしの父の内におり、あなたたちがわたしの内に、そしてわたしがあなたたちの内にいることが分かるであろう」。(二〇節)
「その日には」とは、「別の同伴者」、すなわち「真理の霊」が弟子たちのところに来られる時を指しています。この句は、黙示思想において「人の子」が現れる終わりの日を指して、期待をこめて繰り返される句ですが、ヨハネ福音書はそれを聖霊が到来する日に用います。イエスは御自分の内に父がおられて働いておられることを繰り返し主張してこられました(一〇・三八、一四・一〇~一一)。「その日には」、すなわち聖霊が来られる時には、わたしが言うまでもなく、あなたたち自身がその事実を悟るであろうと、イエスは言われます。原文では「あなたたち自身が」が強調されています。しかも、イエスが父の内におられることだけでなく、「あなたたちがわたしの内に、そしてわたしがあなたたちの内にいること」をも悟るようになると予告されます。ここでは地上のイエスの予告として「分かるであろう」と未来形で語られ、将来の「その日に」起こることとされていますが、実は著者は現在の自分たちの体験を語っているのです。
「父の内に」とか「わたしの内に」また「あなたたちの内に」の「の内に」はみな、前置詞《エン》が用いられています。この《エン》は、パウロが「キリストにあって」《エン・クリストー》という重要な句で繰り返し用いています。パウロにおいては、この句は復活者キリストとの交わりの現実に、福音のすべての内容が含まれていることを指しています。ヨハネもこの《エン・クリストー》の現実を、同じ《エン》を用いてヨハネ流に表現します。
真理の御霊が来られるとき、わたしたちが御霊によって復活者キリストとの交わりに入るとき、わたしたちはイエスが父の内におられ、父がイエスの内におられて、イエスと父は一つであることを悟るだけでなく、わたしたちが復活者イエスの内にいること、そして復活者イエスがわたしたちの内にいてくださることを、霊的体験として悟ります。ヨハネ福音書の「わたし」は復活者イエスの「わたし」ですから、ここで言われていることは、パウロが「わたしはキリストの内に、キリストはわたしの内に」と告白したことと同じです。もし「神秘主義」という用語を、直接的な霊的体験を核とする宗教思想という広い意味で使うならば、パウロもヨハネも神秘主義者であると言えます。両者とも、御霊による復活者キリストとの命の交わりを、その宗教思想の根幹とするキリスト神秘主義者です。
御自身を現されるイエス
「わたしの命令を保持してそれを守る者は、わたしを愛する者である。わたしを愛する者はわたしの父に愛されることになり、わたしもその人にわたし自身を現そう」。(二一節)
先に「もうしばらくすると、世はもうわたしを見ないが、あなたたちはわたしを見る」という表現で、世を去られたイエスを見ることができない世の人々と、復活されたイエスを見る者たちとの峻別が語られました。そして、イエスを見るとは御霊による復活者イエスとの命の交わりであることが明らかにされました。では、どのような人が「イエスを見る」側に入るのでしょうか。
人間は自分の能力で復活者イエスを見ることはできません。それはイエスが御自身を復活者キリストとして現してくださるときに初めて可能になります。では、イエスは誰にご自分を現してくださるのでしょうか。ここでその問が取り上げられ、この問題を主題とする対話が始まります。
イエスは、「わたしを愛する者」に御自身を現すと言われます。「わたしを愛する者」とは、先にも述べましたように、イエスを復活者キリストと信じて告白し、全身全霊をもってこのイエスに自分を委ね、このイエスと結ばれて生きること(すなわち信仰)をヨハネ流に言い表したものです。ただここでは、そのように信じてイエスと結ばれて生きる者が、当然の結果としてイエスの命令を守ることが、イエスを愛することのしるしとして取り上げられます。
「わたしの命令」とは、イエスがこの最後の食事の席で弟子たちに与えた「新しい命令」(一三・三四)を指しています。イエスは弟子たちに、「わたしがあなたたちを愛したように、互いに愛し合いなさい」と言われました。「イエスを愛する者」は、自然にこのような愛をもって生きるようになります。それがイエスを愛することのしるしです。そのような質の愛に生きる者は、父が喜ばれ、父はイエスを愛されたようにその人を愛されます。そのような人をイエスは喜び、御自身を現してくださいます。すなわち、イエスが復活者キリストであるという霊的真理が聖霊によって直接啓示されることになります。信仰はこの啓示体験の上に立ち、信仰者はこの啓示を根拠にして生きます。
イスカリオテでないユダがイエスに言う、「主よ、わたしたちには御自分を現そうとされるのに、世には現そうとされないのは、どうしてですか」。(二二節)
イエスの言葉を聞いて、弟子の一人ユダが不審の思いをぶつけてイエスに訊ねます。
「イスカリオテでないユダ」は、マルコ(三・一六~一九)とマタイ(一〇・二~四)の「十二人」の人名表には出てきませんが、ルカ(六・一六)と使徒言行録(一・一三)には「ヤコブの子ユダ」の名が出てきます。おそらく著者ヨハネはこのユダを指していると見られます。ルカ文書の「ヤコブの子ユダ」は、マルコ・マタイの「十二人」の表との比較から、マルコ・マタイの「タダイ」と同一人物であろうと推察されています。ただ、この箇所の写本が様々な読み方をしているので、どの人物を指すのか学説は混乱しています。このユダの言動が福音書に報告されているのはここだけです。
ユダは、世から孤立し迫害される共同体の疑問を代表してイエスに尋ねます。イエスが復活者キリストであり、神の栄光を現す方であるならば、そのことを少数の弟子集団だけに現して、広く世界に現そうとされないのはなぜか。御自身の栄光を世にも現して、世がすべて救われたキリストの民となるようにされないのはなぜか。黙示思想が待望するように、終わりの日に世のすべての人がイエスの栄光を見るようにされないのはなぜか。ヨハネ共同体が、そして代々のキリストの民が抱くこの疑問を、ユダが代表して訊ねます。
イエスは答えて彼に言われた、「誰でもわたしを愛するならば、わたしの言葉を守る。そうすると、わたしの父もその人を愛されて、わたしたちはその人のところに行き、その人のところに住む」。(二三節)
ユダの質問に対して、イエスはその理由を説明されることはありません。「誰でも」イエスを愛して、イエスの栄光を示される側に入ることができるのですから、イエスの栄光の啓示を受けることができないのは、イエスの側に理由があるのではなく、イエスを愛さない(すなわち信じない)者にその原因があることになります。イエスを愛するか否かによって、世界は二つに峻別されます。イエスを愛さない者には、最後まで復活者イエスの栄光が現されることはありません。こうして、ヨハネの厳しい二分論が貫かれます。
イエスを愛する者はイエスの言葉を守ります。イエスの言葉はイエスを遣わされた父の言葉ですから(次節参照)、イエスの言葉を守る者は、父の言葉を守る者として、父が愛されます。父はその人を愛して、イエスと一緒にその人のところに来て、その人のところに住まわれます。ここの「住むことになる」(未来形)は、先に(一四・二で)「住まいは多い」というところで用いられた「住まい」という語を用いた「住まいをなす」という表現です。
イエスは「わたしたちはその人のところに行き、その人のところに住む」と言われます。その「わたしたち」とは、父とイエス御自身です。イエスを愛する者のところには、復活者イエスと、そのイエスと一体である父が来て住まわれる、とイエスは言われます。先に「別の同伴者」である聖霊が来て、「その霊はあなたたちのもとに留まり、あなたたちの中におられることになる」と言われていました(一四・一七)。そこで見たように、その「別の同伴者」とは、御霊という形でわたしたちの中に働かれる復活者イエスに他なりません。そうすると、イエスを愛する者の内には、父と復活者イエスと聖霊の三者が来て住まわれることになります。復活者イエスはすなわちキリストですから、そしてイエスは父の子ですから、この箇所は父と子キリストと聖霊の(一体である)三者がわたしたちのところに来て、わたしたちの内に住んでくださるという、実に驚くべき宣言です。後世、この父と子と聖霊の関係について、「三位一体論」という精緻な神学論が展開されることになりますが、ヨハネ福音書ではこの三者は一体として(=重なり合って)、イエスを愛する者(=信じる者)の中に実際に宿り働いてくださる方の呼び名に他なりません。
「わたしを愛さない者は、わたしの言葉を守らない。実に、あなたたちが聞いている言葉はわたしの言葉ではなく、わたしを遣わされた父の言葉なのである」。(二四節)
前節で「誰でもわたしを愛するならば、わたしの言葉を守る」と言われていました。同じことがここで、「わたしを愛さない者は、わたしの言葉を守らない」と、否定の形で述べられます。世界はイエスを愛する者たちとイエスを愛さない者たちの二つの陣営に分かれます。その間には融和とか交流はありません。少なくともヨハネはそう見ています。イエスを愛する者たちはイエスの言葉を守ります。それに対して、イエスを愛さない者たちはイエスの言葉を守りません。そして、イエスの言葉は人間イエスの言葉ではなく、イエスを遣わされた父の言葉、すなわち天地の創造者にして救済者である神の言葉ですから、イエスを愛さず、イエスの言葉を守らない者は、神の言葉を拒み、神に背を向ける者となります。こうして世界は、イエスを愛して父・復活者イエス・聖霊を内に宿す民と、イエスを愛さず神に背く世、という二つの領域に峻別されます。
「これらのことは、わたしがあなたたちのもとに留まっていたときに語ってきた」。(二五節)
ここで言われたことは、イエスが弟子たちと一緒におられた時に語られたことを繰り返し、要約するものです。福音書には、イエスが地上におられた時に語られた言葉を記録して伝えるという一面、すなわちイエスの語録集という一面があります。共観福音書はとくにその面が前面に出ています。それに対してヨハネ福音書は、その一面もありますが、それ以上にもう一つの面が強く出ています。そのもう一つの別の面が次節で説明されます。「だが、かの同伴者、すなわち父がわたしの名によって遣わされる聖霊であるが、その方があなたたちにすべてのことを教え、わたしがあなたたちに話したことを思い起こさせてくださる」。(二六節)
先に、去って行かれるイエスの代わりに「いつまでも一緒にいてくださる」《パラクレートス》(同伴者)が約束されました。今ここで、その「同伴者」とは「父がわたしの名によって遣わされる聖霊」であると明言されます。「聖霊」という表現は、ヨハネ福音書ではここと一・三三、二〇・二二の三箇所だけですが、「真理の霊」とか「御霊」という形で、その方の働きがこの訣別遺訓の中心主題となっています。その《パラクレートス》の役割(すべてではないが重要な役割の一つ)は、「すべてのことを教え、わたしがあなたたちに話したことを思い起こさせ」ることであると言われます。ヨハネ福音書は、この《パラクレートス》の働きによって「思い起こされた」イエスの言葉を世に伝える書です。すなわち、たんに伝承されたイエスの言葉を伝えるのではなく、いま共同体の中に働く聖霊によって、共同体が現に聴いている復活者イエスの言葉を世に伝えるために書かれた書なのです。
ヨハネ共同体は、聖霊によって自分たちが今体験している復活者イエスを言い表すためにこの福音書を生み出しましたが、それを単に自分たちの体験の告白として語るのではなく、あくまでイエスの言葉として語るのです。そこにこの福音書の二重性があります。すなわち、この福音書の言葉はイエスの言葉であると同時に、ヨハネ共同体の告白の言葉でもあるのです。その二重性がここで、「聖霊が(イエスの言葉を)思い起こさせる」という表現で示されています。
福音書が福音書である限り、伝承されたイエスの言葉を伝えるという面と、イエスを復活者キリストとして告白する言葉という面の両面があり、この両面は相互に浸透し合って、複雑な二重性を形成しています。ヨハネ福音書においてはこの二重性がきわめて独特の形をとっており、イエスの言葉とヨハネ共同体の告白の言葉が「継ぎ目なく」溶けこんでいます。この福音書を読むときには、この独自の二重性を理解して読む必要があります。そして、この独自の二重性がこの福音書の魅力であり、また難しい課題です。
わたしの平安を与える
「わたしはあなたたちに平安を残していく。わたしの平安をあなたたちに与える。世が与えるようにではなく、わたしが与える。あなたたちは心を騒がせず、恐れないでいなさい」。(二七節)
「平安」のギリシア語原語《エイレーネー》は、ヘブライ語の《シャローム》の訳語として、平和とか平安という一語では表現できない内容を含んでいます。しかしここでは、一四章一節の心騒ぎの反対の状態を指す語として用いられ、「心を騒がせず、恐れないでいる」ことを内容としているので、「平安」と訳してよいでしょう。「あなたたちは心を騒がせないがよい」で始まったこの章(一四章)は、この平安を与える約束で締め括られます。イエスは「わたしの平安」を与えると言われます。その「わたしの平安」の意味は、すぐ後に続く文が説明しています。すなわち、「世が与えるようにではなく、わたしが与える」平安だということです。イエスが与えてくださる平安は、世が与える平安とは随分違います。
人はみな平安を願います。人間の営みはみな、結局は平安を確保するためであると言ってもよいくらいです。身体の平安は健康です。身体のトラブルである病気から解放されて健康でいるために医療施設や薬を準備しています。また、対人関係や社会生活のトラブルから解放されて平穏な生活を維持するために、警察や裁判所などの制度を発達させています。経済的な破綻を免れるためには保険制度が維持されています。軍備さえも国という生活基盤が平安であるためとされます。国連も世界の平安を維持するための国際組織です。このように、世界は平安を確保するための装置であると言ってもよいほどです。そして、人々はその装置のために巨額の費用を払い、日夜努力を続けています。このような世界の装置が保障してくれる平安が「世が与える平安」です。
しかし、このような「世が与える平安」はしばしば破綻します。そのような装置ではどうしても平安を確保できない時があります。人間が地上で生きていくとき、まったく心を騒がせないで生きることは不可能であるようです。それだけでなく、平穏な人生を送れたとしても、人間には死の不安とか、存在の無意味さへの怖れとか、魂の奥底に抱える不安とか怖れがあります。
このような不安の中にいる人間に、父から遣わされ、再び父のもとに帰ろうとされるイエスは、「わたしはあなたたちに平安を残していく」と言われます。父のもとに帰られるイエスが世にいる者たちに残していかれる平安は、復活されたイエスが「別の同伴者」を送ってくださり、その「同伴者」によって内面の奥深くに生じる平安です。力強い同伴者がいつも傍にいてくださる魂の平安です、すなわち、聖霊による生の充実、その充実による不安や苦悩の克服、生を脅かす力にたいする勝利、確かな約束に基づく輝かしい将来への希望、このような聖霊の実から生じる平安が、イエスが与えてくださる平安、「わたしの平安」です。パウロも御霊の結ぶ実の中に「平安」をあげています(ガラテヤ五・二二)。
「あなたたちは、『わたしは去っていくが、また戻って来る』とわたしが言うのを聞いた。もしわたしを愛しているのであれば、あなたたちはわたしが父のもとに行くことを喜んだことであろう。父はわたしよりも大いなる方であるから」。(二八節)
イエスが「わたしは去っていく」と言われたので、弟子たちは心配し、不安に心を騒がせていますが、イエスは父のもとに行かれるのですから、弟子たちはイエスが去られることを喜ぶべきなのです。イエスは父のもとに行き、ご自分に属する者たちを父の家に迎えるために「また戻って来る」と言われるのですから、イエスをそのような方と信じるのであれば、この別れを喜ぶことができるはずだと言われます。そして、喜ぶ理由として、イエスが「より大いなる方」のところに行かれるのだから、という文が加えられます。イエスは、ご自分が父から遣わされた者であると自覚し、自分がそういう者であることを繰り返し語ってこられました。遣わした者は遣わされた者よりも、存在の序列においてより上位にあります。そのことが「父はわたしよりも大いなる方である」と表現されます。この文を根拠にして、父と子の神性や能力の大小を議論することは場違いです。
「そして今、ことが起こる前にあなたたちに言っておく。ことが起こったとき、あなたたちが信じるようになるためである」。(二九節)
「ことが起こる」というのは、目前に迫っているイエスの最後のことです。刑死という最後は、イエスが父から遣わされた方であると信じることの妨げになります。事実多くのユダヤ人はローマ総督によって処刑されたイエスをメシアと信じることを拒否しました。しかし、そのことが起こる前に言っておくことによって、それが神の御計画の中にあること、したがってイエスが神の御計画によって遣わされた方であると受け取ることができるようになります。「あなたたちの間で多くを語ることは、もはやないであろう。世の支配者が来るからである。彼はわたしに何のかかわりもない」。(三〇節)
時は迫っています。これ以上多くのことを語る時間はないとして、イエスはここで話を打ち切られます。イエスは、自分を逮捕しようとする勢力が行動を開始していることを見通しておられます。それを「世の支配者が来る」と表現されます。「世の支配者」とは、ヘレニズム世界(とくにグノーシス主義)の用法では、「世」《コスモス》を支配する霊的存在を指します。《コスモス》(宇宙)は数層の霊界からなっており、それぞれの層に《アルコーン》(支配者)がいると考えられていました。ここの《アルコーン》は単数形ですが、これは諸々の《アルコーン》たちの総称と考えられます。この世《コスモス》を支配する《アルコーン》が、ユダヤ教の支配層やローマの支配者たちを用いて、父が世に遣わされたイエスを殺そうとして近づいてきているのです。著者は、イエスを逮捕するために来る軍勢の背後に、このような霊的な力の働きを見ています。
しかし、彼(世の支配者)はイエスに対しては支配権をもっていません。ここの直訳は「彼はわたしの中に何も持っていない」となります。彼は世《コスモス》を支配していますが、世に属さないイエスには何の権力ももっていません。イエスが逮捕され、彼らに身を委ねられるのは、《アルコーン》の支配に陥るからではなく、イエスが進んで父の御心を行うためであることが、次節で明言されます。
「しかし、わたしが父を愛していることを世が知るようになるために、わたしは父がお命じになったとおりに行うのである。さあ、立て。ここから出ていこう」。(三一節)
新改訳、新共同訳、岩波版は「わたしが父を愛していること」と、「わたしは父がお命じになったとおりに行うこと」の両方を、「世が知るようになる」ことの内容としています。しかし、この訳では「世が知るようになるために」という目的が宙に浮いてしまって、どの行為の目的を示しているのか、また先行する文との脈絡が理解できなくなります。ここはRSVとか協会訳のように、「世が知るようになる」の内容は「わたしが父を愛していること」だけにして、それが「わたしは父がお命じになったとおりに行う」ことの目的を示していると理解すべきであると考えられます。そうすれば、先行する「世の支配者はわたしと何のかかわりもない」という文との脈絡も理解できます。すなわち、「世の支配者」はわたしに何の関わりもなく、わたしに何も強制はできないのであるが、わたしが父を愛していることを世が知るようになるために、わたしは自ら進んで父の定めである受難の道を行くのである、という意味がはっきりします。ここまで語って、イエスは弟子たちに「さあ、立て。ここから出ていこう」と言われます。この言葉によって、最後の食事の席における弟子たちへの訓話は終わっています。それにもかかわらず、「訣別遺訓」は一五章から一七章にかけて長々と続き、一八章一節になってようやく、「さあ、立て。ここから出ていこう」という言葉に自然に続く文が出てきます。それで、本来の「訣別遺訓」は一四章で終わっていたのであるが、後で一五~一七章の部分が加えられて現在の形になったものと推定されています。この推定について、またこの部分の成立状況については、一五章に入るときに考察することにします。

















